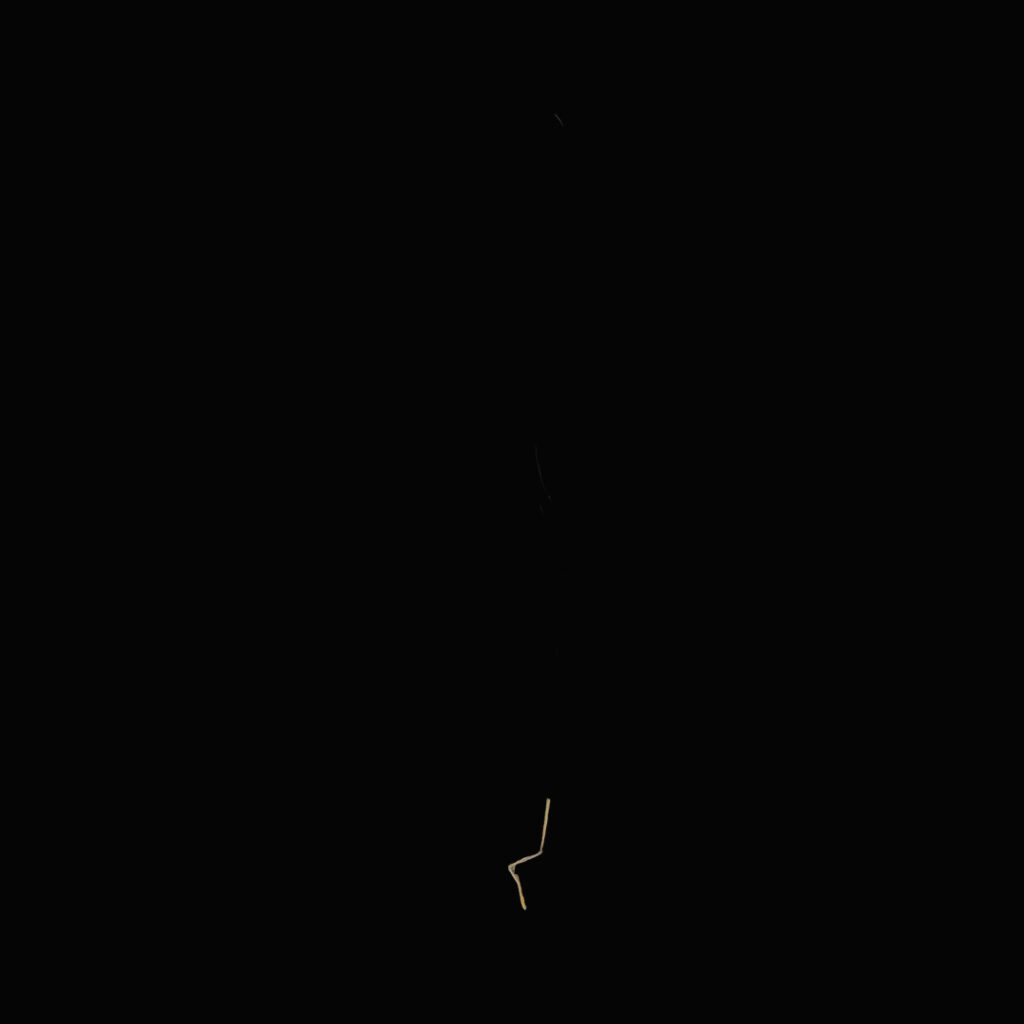
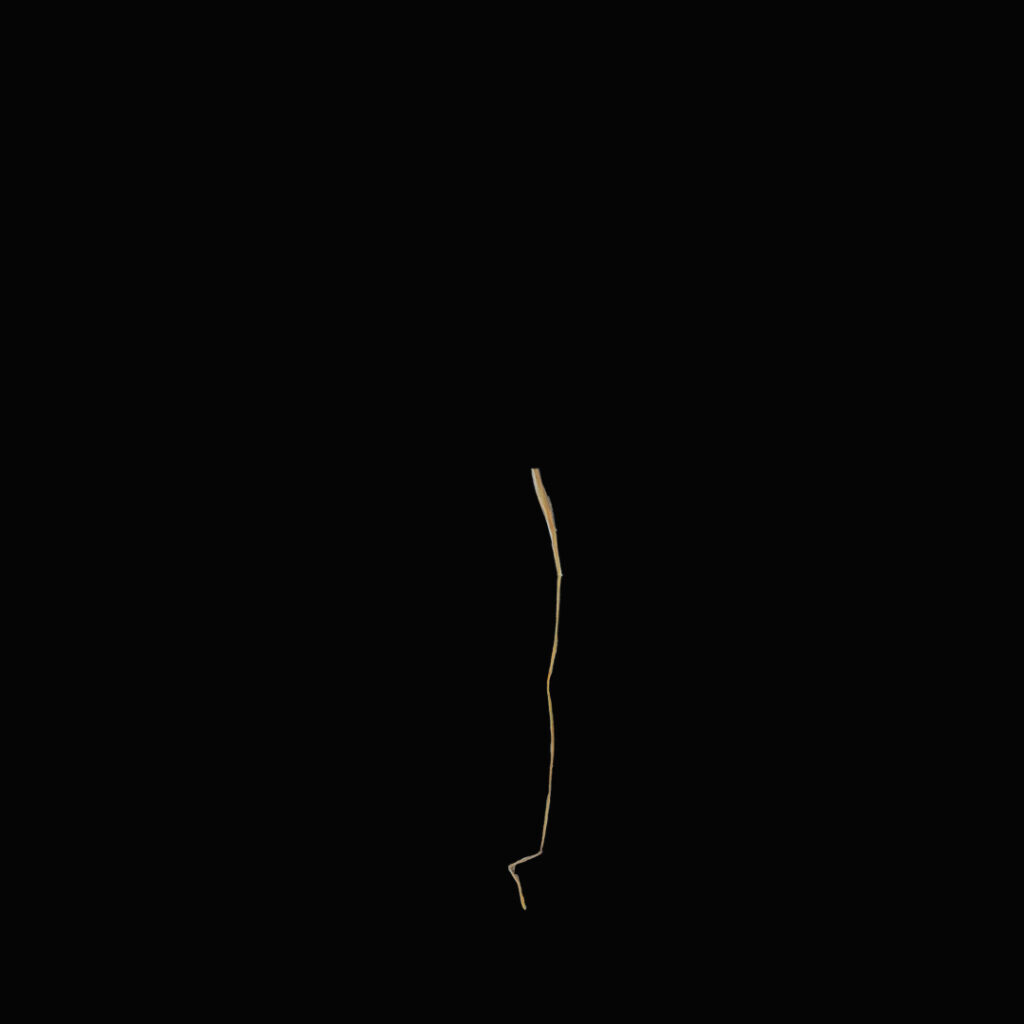

豆もやしを描く
キミ子方式という絵の描き方があります。
(詳しくはこちらから)
モチーフを見ながら
見ているところを完成させて描いていく
絵が紙からはみ出しそうになったら、紙を足して
とにかく描くことを楽しむ!
そんな描画法です。
このキミ子方式で
代表的なモチーフといえば豆もやし。
真っ黒な画用紙に
徐々に姿を現していく描き方は
とてもワクワクします。
豆もやしは細くて色数も少なく
描ききることができるところも魅力
完成させることができると
次の制作へのモチベーションも上がりますね。
本来キミ子方式では三原色で描きますが
今回はアクリル絵の具で色数制限せず
細密に描写しました。
描画のポイントは
・あっという間に変色するので潔く描く
・もやしの根から本体へ向かう微妙な変化をよく観察する
・筆先が利く筆を選ぶ
もやしの少し黄みがかった色は
イエローオーカーやピロールレッド
カドミウムイエロー
隠し味にサップグリーンなども使用しました。
細密描写は、色の構造を理解するのに
大変勉強になります。
もやし本体に反射光を引くと
細さなりの立体感が描けます。
また、もやしの透明感をどうやって出すかを考えた末
今回は薄色を重ねず、都度その色をつくり
もやし本体の中にあるハイライトと中間色
反射光と影の部分を細かく描写していきました。
色の計算式
わたしは今まで
モチーフの色を再現しようと
沢山絵の具に触れてきました。
初心者の頃は、混ぜすぎて
とんでもない色をつくり
結局使えなくて
捨ててしまうこともしばしば。
でも、ある時から
色を再現するコツのようなものがわかってきて
試行錯誤するうちに
色の構造を読み解く力がつきました。
それは
「少しくすんだ色を出したいときは
この色とこの色を混ぜる」や
「下地に先ずこの色を差しておいて
乾いたら、この色を置いてゆく」など
自分なりの色の計算式を覚えて
アウトプットしていくことと
同時進行でした。
実際に手を動かしてアウトプットするから
外からも色の構造が見えてくる
そんな感じでしょうか。
自分なりの計算式が体内にあるからこそ
色の重なりのイメージが
経験として
知覚できるのかもしれません。
なので、初心者の方は早い段階で
色の足し算、引き算、掛け算、割り算を
何度も繰り返したくさんおこない
自分なりの式を見つけてください。
そうすれば、きっと描写が
ぐんぐん楽しくなりますよ。
